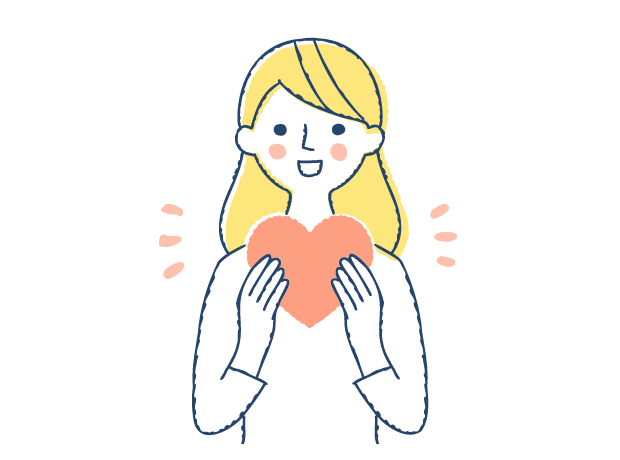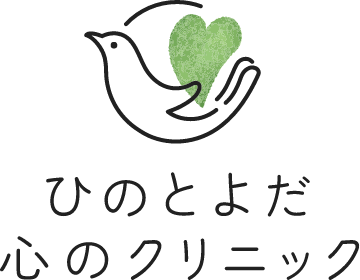神経発達症(発達障害)
神経発達症(発達障害)の症状・原因
神経発達症は生まれつきの脳の発達の違いによるものです。多くの場合はこどもの頃からその特性が現れますが、その特性を個性の一つとして捉えられたり、周りのフォローが得られることで、特に問題にならずに大人になることも少なくありません。しかし、進学や就職で社会に出ると、いろんな人とコミュニケーションをとったり、場の空気を読んだり、周囲に合わせたりと、人間関係が複雑となります。また、学業や仕事においては、マルチタスクを求められたり、優先順位をたてたり、それらを計画的に進めるなど、周りとの関係の中でやるべきことを意識し遂行する機会が増します。このため、大人になってから元々持っていた発達の特性が浮かび上がることがあるのです。

以下に、代表的な自閉症スペクトラム症と注意欠如・多動症の症状について説明していきます。
自閉症スペクトラム症(ASD)
- 言葉や視線、表情、身振りなどで他人とコミュニケーションをとるのが苦手
- 相手の気持ちを読み取ったり、自分の気持ちを伝えることが苦手だが、興味・関心のあるものには集中しすぎたり、こだわりが強い
- 音や光や臭いなど感覚に敏感である
- 課題や作業をしていてもすぐに他に関心が移り、集中し続けられない、段取りが苦手
- 忘れ物や失くし物が多い
- 落ち着かない、考えるよりも先に行動してしまう
これらの特性により、相手と会話がかみ合わなかったり、悪気なく相手を怒らせてしまったり、臨機応変な対応が苦手などの、社会生活におけるつまずきが生じやすくなります。一方で、ルールを守り、行動に表裏がなく誠実なところや、特定分野における目を見張るような知識の豊富さや、ひとつのことを日々コツコツと継続する力など、すばらしい側面も持ち合わせています。
注意欠如・多動症(ADHD)
- 注意が散漫となりやすく、集中力が続かない
- 落ち着きがない、待つことができない
これらの特性により、ケアレスミスが多かったり、忘れ物や落とし物、遅刻が多かったり、スケジュール管理やタスク管理が苦手などの、社会生活におけるつまずきが生じやすくなります。一方で、発想力や創造力に富み、行動力や決断力があり、興味のあることに対しては抜群の集中力を発揮するなど、すばらしい側面も持ち合わせています。
神経発達症(発達障害)の診断
DSM-5*におけるASDの診断基準
以下のA、B、C、Dを満たしていること。
社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害(以下の3点で示される)
- ( 1 ) 社会的・情緒的な相互関係の障害。
- ( 2 ) 他者との交流に用いられる非言語的コミュニケーション(ノンバーバル・コミュニケーション)の障害。
- ( 3 ) 年齢相応の対人関係性の発達や維持の障害。
限定された反復する様式の行動、興味、活動(以下の2点以上の特徴で示される)
- ( 1 ) 常同的で反復的な運動動作や物体の使用、あるいは話し方。
- ( 2 ) 同一性へのこだわり、日常動作への融通の効かない執着、言語・非言語上の儀式的な行動パターン。
- ( 3 ) 集中度・焦点づけが異常に強くて限定的であり、固定された興味がある。
- ( 4 ) 感覚入力に対する敏感性あるいは鈍感性、あるいは感覚に関する環境に対する普通以上の関心。
症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになるものもある。
症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている。
DSM-5*におけるADHDの診断基準
持続する不注意あるいは多動/衝動性行動パターン(ないしはその両者)で以下の(1)あるいは(2)(ないしはその両者)の特徴のために生活機能や発達に支障をきたしている
-
( 1 ) 不注意:下記のうち6つ(あるいはそれ以上)の症状が少なくとも6か月以上持続し、またそれらの行動特徴が発達レベルと合わず、社会生活や学業・就業に直接悪影響を与えている
-
※これらの症状は、反抗や挑戦、敵愾心によるもの、あるいは課題や指示を理解できないためではない。思春期以降の年長者や成人(17歳以上)では少なくとも5つ以上の症状を満たすこと
- ( a ) 細かいことに注意がいかない、あるいは学業や仕事、そのほかの活動においてケアレスミスをしばしばおかす
- ( b ) 課題や遊びにおいて、しばしば注意を持続することが困難である
- ( c ) 直接話しかけられても、聞いているようには見えない
- ( d ) 出された指示を最後までやり遂げられない。また命じられた学業の課題や仕事、家事を終わらすことができない
- ( e ) 課題や活動を順序立てて行うことが困難である
- ( f ) 精神的努力を要するような課題を避けたり、嫌がる。あるいは嫌々行う
- ( g ) 課題や活動に必要なものを失くす
- ( h ) 外からの剌激で気が散りやすい
- ( i ) 日常生活で忘れっぽい
-
-
( 2 ) 多動と衝動性:下記のうち6つ(あるいはそれ以上)の症状が少なくとも6か月以上持続し、またそれらの行動特徴が発達レベルと合わず、社会生活や学業・就業に直接悪影響を与えている
-
※これらの症状は、反抗や挑戦、敵愾心によるもの、あるいは課題や指示を理解できないためではない。思春期以降の年長者や成人(17歳以上)では少なくとも5つ以上の症状を満たすこと
- ( a ) 手や足をそわそわと動かしたり、身をよじったりすることが多い
- ( b ) 教室内など座っていることが求められる状況で、席を離れる
- ( c ) しばしば、そうすることが不適切な状況で、走り回ったり、高いところによじ登ったりする
- ( d ) 静かに遊ぶことができない
- ( e ) じっとしていられず、まるでエンジンで駆動されるように行動する
- ( f ) 過度のおしゃべりが多い
- ( g ) 質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう
- ( h ) 順番を待つことが困難である
- ( i ) 他者の行為を遮ったり、割り込んだりする
-
不注意、あるいは多動・衝動行動のいくつかは、12歳以前に存在していること
不注意、あるいは多動・衝動行動のいくつかは、2つ以上の状況でみられること(例:家庭内、学校、あるいは職場;友人や親戚と一緒にいるとき;その他の活動において)
これらの症状が明らかに社会生活、学校生活あるいは仕事上での機能を妨げ、あるいは低下させている事実があること
統合失調症やその他の精神疾患の症状発現時のみに現れることはないし、その他の精神疾患によって説明されないこと(例:うつ病、不安障害、解離性障害、パーソナリティ障害、薬物乱用あるいはその離脱症状など)
不注意優勢型と診断するには,6つ以上の不注意の症候が必要である。多動性・衝動性優勢型と診断するには,6つ以上の多動性・衝動性症候が必要である。混合型と診断するには,不注意と多動性・衝動性のそれぞれで6つ以上の症候が必要である。
*DSM-5:Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
神経発達症の診断に際しては、診断を受けるメリットとデメリットを考える必要があります。例えば本人がASDの特性や症状で困っており、診断を受けることで症状や状況の改善が得られる場合などです。神経発達症はそれぞれが重なりあうこともあります。また、偏りの差には個人差がありますので、診断に際してはご本人やご家族のお話だけではなく、必要に応じて心理検査を行います
神経発達症(発達障害)の治療
治療や支援内容は、年齢や環境、ライフステージによっても変化します。大人になって気づかれる場合は、社会生活の困難さから二次的に抑うつなどの精神症状を呈していることが多いため、一人一人の困りごとをお聞きしながら症状に対して治療を行います。
そのあとで、改めてご自身の発達特性に目を向け、理解を深めたり対処方法を身につけていくことで日常の困りごとを減らす工夫をします。また、必要に応じて障害福祉サービスを得られるように支援体制を整え、相談先を増やしたり、デイケアなどの心理社会的リハビリを行います。
ADHDに対しては有効とされる薬物療法があり、不注意や衝動性に対する効果が期待できます。詳しくは当院にてぜひご相談ください。