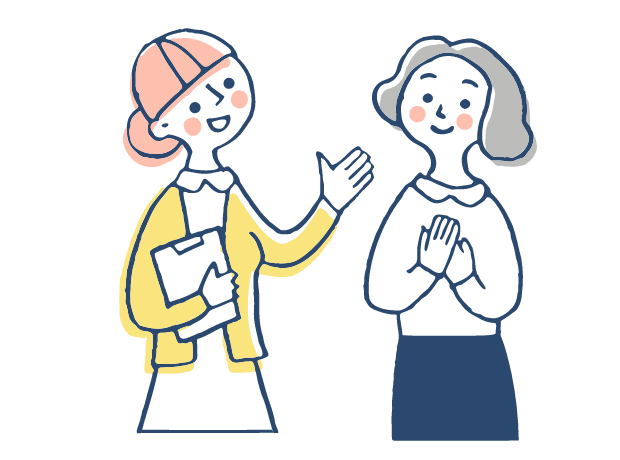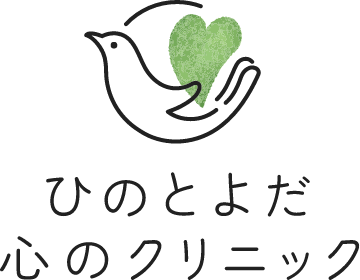統合失調症
統合失調症の症状・原因
統合失調症は、考えや気持ちがまとまらなくなり、自分と他者との境界があいまいになる病気です。そのため、気分や行動に影響が出て、学業や仕事などの日々の暮らしに支障が生じます。
以下にあげるような陽性症状、陰性症状、認知機能障害、感情障害が認められます。
統合失調症の原因はまだ明らかとなっていませんが、遺伝的要因や環境的要因など様々な要因が重なり、脳内の神経伝達物質「ドパミン」のアンバランスや神経発達の異常が生じるといわれています。

陽性症状
幻覚
いない人の声が聞こえる、その声と会話している
妄想
悪口を言われている、監視されていると思う
思考障害
考えが矛盾しまとまらない
自我障害
自分と他者との境界があいまいになり、自分の考えがまわりに伝わっているとか、誰かにあやつられていると感じる
陰性症状
感情鈍麻
感情の動きが少なくなる / やる気が出ず、自分から何かを行おうという意欲が低下する
思考の低下
言葉が少なくなり、会話の豊かさが失われる
無為・自閉
他人とのかかわりを避け、閉じこもるようになる / 人柄が変わったように見える
認知機能障害
集中力、注意力の低下
仕事や学業に集中できなくなる
記憶力の低下
物事を覚えるのに時間がかかるようになる
判断力の低下
ものごとを理解し、優先順位をつけたり計画をたてることが難しくなる
感情障害
気分の落ち込み、不安、眠れなくなる
気分が高揚し、興奮、イライラしやすくなる
統合失調症の診断
DSM-5*による統合失調症の診断基準
以下のうち2つ(またはそれ以上)、おのおのが1か月以上(または治療が成功した際はより短い期間)ほとんどいつも存在する。これらのうち少なくとも1つは(1)か(2)か(3)である。
- ( 1 ) 妄想
- ( 2 ) 幻覚
- ( 3 ) まとまりのない発語(例:頻繁な脱線または滅裂)
- ( 4 ) ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動
- ( 5 ) 陰性症状(すなわち感情の平板化、意欲欠如)
障害の始まり以降の期間の大部分で、仕事、対人関係、自己管理などの面で1つ以上の機能のレベルが病前に獲得していた水準より著しく低下している(または、小児期や青年期の発症の場合、期待される対人的、学業的、職業的水準にまで達しない)。
障害の持続的な特徴が少なくとも6か月間存在する。この6か月の期間には、基準Aを満たす各症状(すなわち、活動期の症状)は少なくとも1か月(または、治療が成功した場合はより短い期間)存在しなければならないが、前駆期または残遺期の症状の存在する期間も含んでよい。これらの前駆期または残遺期の期間では、障害の兆候は陰性症状のみか、もしくは基準Aにあげられた症状の2つまたはそれ以上が弱められた形(例:奇妙な信念、異常な知覚体験)で表されることがある。
統合失調感情障害と「抑うつ障害または双極性障害、精神病性の特徴を伴う」が以下のいずれかの理由で除外されていること。
- ( 1 ) 活動期の症状と同時に、抑うつエピソード、躁病エピソードが発症していない。
- ( 2 ) 活動期の症状中に気分エピソードが発症していた場合、その持続期間の合計は、疾病の活動期および残遺期の持続期間の合計の半分に満たない。
その障害は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。
自閉スペクトラム症や小児期発症のコミュニケーション症の病歴があれば、統合失調症の診断は、顕著な幻覚や妄想が、その他の統合失調症の診断必須症状に加え、少なくとも1か月(または、治療が成功した場合はより短い)存在する場合にのみ与えられる。
*DSM-5:Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
統合失調症の治療
統合失調症の治療には、抗精神病薬を中心とした薬物療法をはじめとし、病気の理解を深めたり安定した生活を送る能力を伸ばすための心理社会的なリハビリテーションを行います。
薬物療法
抗精神病薬を中心に薬物治療を行います。脳内の神経伝達物質「ドパミン」のアンバランスを改善させる作用があり、幻覚や妄想の改善が期待できます。また、不眠や不安、気分の不安定さに対する効果をもつものもあります。効果や副作用の出現については個人差が大きいため、患者様の「お薬の飲み心地」を大切にしながら薬物調整を行います。
また、これらの抗精神病薬の中には、毎日の内服薬で精神症状の改善や安定を目指すほかに、貼り薬や、月に一度の注射剤があります。効果や副作用についてはもちろん、おひとりおひとりに合った薬物療法の選択をご提案します。
統合失調症は再発しやすい病気のため、よくなった後も治療を継続し、症状の安定と回復を目指していく必要があります。
心理社会的なリハビリテーション
診察の中で、主治医との対話を通じて病気や治療への理解を深め、幻聴や妄想に起因する困りごとについて、その対処法を考えていきます。
また、作業療法やデイケアなどの集団リハビリテーションに参加することで、生活リズムを安定させ、他者交流人を通して社会性を伸ばしたり、感情の安定や意欲の改善を目指します。
まずはぜひお話をお聞かせてください。適切な診断のもと薬物療法を行うことで、症状の改善やこれまでの社会生活の維持・回復を期待することができます。