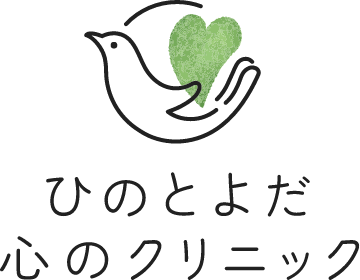不眠障害(不眠症)
不眠障害(不眠症)の症状・原因
不眠障害とは、以下の症状によって、必要な睡眠時間が十分に取れず、仕事や学業等、日々の生活に支障をきたす状態のことです。
寝付けない(入眠困難) 朝までに何回も目が覚める(中途覚醒) もっと寝たいのに早く目が覚める(早朝覚醒) 眠りが浅い(熟睡障害)
睡眠には心身の回復や免疫機能を強化する働きがありますが、不眠が続くことで日中の疲労感、集中力の低下等がみられるほか、うつ病などのメンタル疾患や、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の発症リスクが高まると言われています。
不眠障害の原因は人によってさまざまなので、対処方法や治療方法も異なります。どんな原因による不眠なのかを考えてみましょう。

心理的原因
プライベートや仕事上の不安や心配事など、ある心理的ストレスを契機として睡眠がとりづらくなる。
身体的原因
ケガによる痛み等、身体の病気や症状が原因。
生理学的原因
勤務シフトや時差ぼけ、受験勉強による徹夜など、体内時計の乱れや光暴露の不足など睡眠をさまたげる環境によるもの。
他のメンタル疾患に伴う不眠
うつ病をはじめ、様々なメンタル疾患にともなって生じるもの。
薬理学的原因
服用している薬や、アルコール、カフェイン、ニコチンなどが原因で生じるもの
不眠障害(不眠症)の診断
DSM-5における不眠障害の診断基準
睡眠の量または質への不満に関する明らかな訴えが、以下の症状のうち一つ(またはそれ以上)を伴っている
- ( 1 ) 入眠困難(子どもの場合は、寝かしつけをする人がいないと入眠できない等)
- ( 2 ) 頻回の覚醒、または覚醒後に再入眠できないことによって特徴づけられる睡眠持続困難(子どもの場合は、寝かしつけをする人がいないと再入眠できない等)
- ( 3 ) 早朝覚醒があり、再入眠できない
その睡眠の障害は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、教育的、学業的、行動上、またはほかの重要な領域における機能の障害を引き起こしている
少なくとも1週間に3夜で起こる
少なくとも3か月間持続する
睡眠の適切な機会があるにも関わらず起こる
他の睡眠-覚醒障害(例:ナルコレプシー、呼吸関連睡眠障害、概日リズム睡眠-覚醒障害、睡眠時随伴症)では十分に説明されず、またその経過中にのみ起こるものではない
物質(例:乱用薬物、医薬品)の生理学的作用によるものではない
併存する精神疾患および医学的疾患では、顕著な不眠の訴えを十分に説明できない
該当すれば特定せよ
非睡眠障害性の併存する精神疾患を伴う
物質使用障害を含む他の医学的併存疾患を伴う
他の睡眠障害を伴う
該当すれば特定せよ
一時性:症状は、少なくとも1か月以上持続するが3か月は超えない
持続性:症状は、少なくとも3か月以上持続する
再発性:1年以内に2回(またはそれ以上)のエピソードがある
*DSM-5:Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
不眠障害(不眠症)の治療
睡眠衛生を考える
睡眠衛生の基本
- 朝日を浴びる
- 夜は暗い環境で過ごす
- 規則正しい食生活をおくる
- 昼間光を浴びる
- 規則正しい睡眠
1日24時間であるのに対して、ヒトの体内時計は、約25時間でリズム(生体リズム)を刻みます。光はこのズレを修正するために必要なものなので、朝日を部屋に入れたり、昼間光を浴びたり、寝る前にはパソコンや携帯電話の利用を控えて明るさを抑える必要があります。
また規則正しい食事は、生体リズムを整える大切な要素です。できる限りしっかり3食を同じ時間帯にで、摂るよう心がけてください。
休み前だからといって夜更かししたり、平日眠れなかった分、休日に寝坊し過ぎると生活リズムが崩れてしまう可能性があります。休日も普段と同じ時刻に就寝・起床するよう心がけましょう。多く眠りたい場合は、平日との差を1時間~2時間までにしましょう。
適切な睡眠習慣を保てるよう睡眠環境を工夫したり、睡眠の妨げになる要因についても検討しましょう。ストレスはもちろん、運動不足、お酒やカフェインなどの嗜好品などがあげられます。眠れないからと言って寝酒が習慣化すると、逆に浅い睡眠となり不眠の悪化につながります。
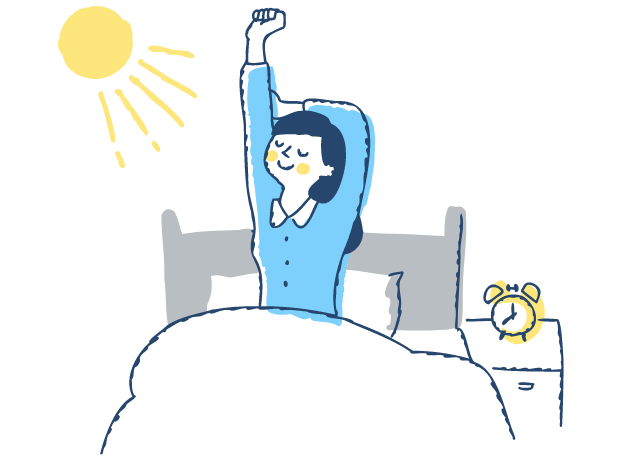
薬物療法
睡眠衛生を整えても不眠症状が改善しない場合には薬を用いた治療を行います。薬に頼らなくても十分な睡眠が得られるようになることを目標に、お薬は必要最小限とし、睡眠の改善がみられたあとは徐々に服用量を減らしていきましょう。不眠症治療薬にはいくつかの種類があり、それぞれに効果が出るまでの時間や、持続時間、脳のどの部分に作用するのかが異なります。お一人お一人のニーズに合わせた薬物療法をご提案しますので、つらい状況を我慢したりせず、ぜひ当院へご相談ください。