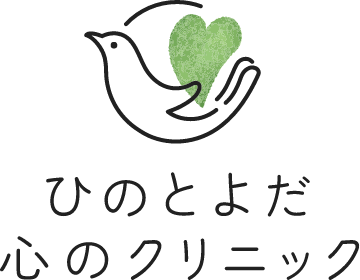適応障害
適応障害の症状・原因
適応障害とは、特定のストレスに対する心理的な反応が、通常の範囲をこえて現れ、社会生活に支障をきたす状態をいいます。転職や異動、生活環境の変化、人間関係の悪化など、ストレス因が明確に特定でき、「そのストレスがなければ今の不調は生じなかった」と考えることができるのが特徴です。
症状は個人差が大きく、抑うつ気分、不安、不眠といった精神症状から、頭痛や胃腸の不調といった身体症状まで、さまざまな形で現れることがあります。診断においては、症状の重症度や持続期間、社会生活への影響度などが総合的に評価されます。
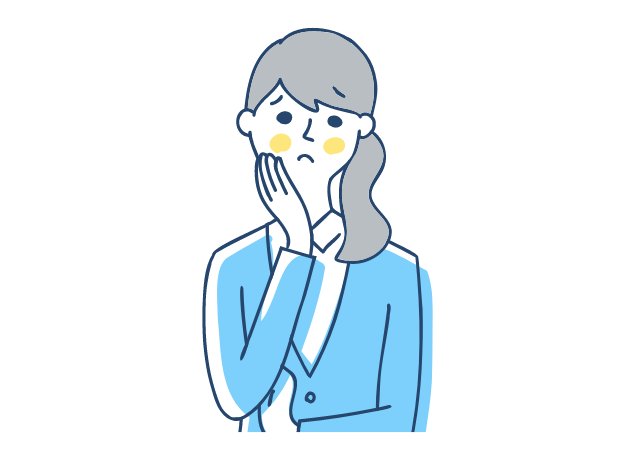
適応障害とうつ病は症状が似ていますが、主な違いは、うつ病では発症のきっかけとして明確なストレス因が特定できない場合もある一方で、適応障害では明確なストレス因が特定でき、そのストレス因との関連性が時間的にも因果関係的にも明確なことです。
症状の面では、適応障害は比較的軽度から中等度の症状を示すことが多く、ストレス因への反応として理解できる範囲内であることが特徴です。これに対し、うつ病ではより重度の症状が現れ、特に気分の落ち込みや意欲の低下が顕著で、日常生活全般に広範な支障をきたすことが多くなります。
経過においても大きな違いがあります。適応障害は、ストレス因が解消されるか新しい環境への適応が進むと、一般的に6カ月以内に症状が改善する傾向があります。一方、うつ病は、原因となる要因が改善しても症状が持続したり、再発を繰り返したりすることが特徴的です。
適応障害の診断
DSM-5による適応障害の診断基準
はっきりと確認できるストレス因に反応して、そのストレス因の始まりから3ヵ月以内に情動面または行動面の症状が出現。
これらの症状や行動は臨床的に意味のあるもので、それは以下のうち1つまたは両方の証拠がある。
- ( 1 ) 症状の重症度や表現型に影響を与えうる外的文脈や文化的要因を考慮に入れても、そのストレス因に不釣り合いな程度や強度をもつ著しい苦痛。
- ( 2 ) 社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の重大な障害。
そのストレス関連障害は他の精神疾患の基準を満たしていないし、すでに存在している精神疾患の単なる悪化でもない。
その症状は正常の死別反応を示すものではない。
そのストレス因、またはその結果がひとたび終結すると、症状がその後さらに6ヵ月以上持続することはない。
*DSM-5:Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
適応障害の治療
薬物療法
上記のアプローチを行いながら、必要に応じて薬物療法を検討します。気分の落ち込みや不安に対してSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬の内服を行います。ただし、抗うつ薬の効果が出るまでには2~4週間要するため、効果が安定するまでの期間、強い不安感や動悸などの自律神経症状に対して抗不安薬を用いることがあります。この抗不安薬については、正しく使用することでつらい不安症状を和らげることができる一方、依存性(抗不安薬を飲まないと落ち着かなくなる)や耐性(漫然と使用することで効果が減弱すること)が生じることがあるため、短期間や頓服使用とすることが望ましいです。
適応障害の薬物療法は「症状に対して薬を使う」という対症療法になので、根本的な治療ではありません。つまり適応障害の治療は薬物療法だけではうまくいかないことが多いため、環境調整やストレスとの付き合い方を工夫することが重要となります。
環境調整や適応力を高める方法が効果的に進めば、症状は早期に消失し社会復帰もうまくいく場合が多いです。ただし、服薬に頼りすぎたり、自身の適応力を高める努力を怠れば慢性的に経過する場合もあり、よくなったり悪くなったりしながらうつ病などの病気に転換される場合もあります。上記のような出来事や症状に思い当たる場合は、当院にご相談ください
非薬物療法
まずは、可能な場合はストレス因と距離をとることです。職場環境や人間関係に関するストレスであれば、上司や産業医に相談して、たとえば席替えや担当替えなどの可能な環境調整・業務調整を依頼してみましょう。一方、ストレス因によってはすぐに状況を変えることが難しいことも多いと思います。また、ストレスをストレスと感じる人とそうでない人がいるように、ストレス耐性は人によってもさまざまです。
ストレスによって心身の不調をきたしやすい場合には、ストレスの受け止め方や対処法についても考え、ストレスへの適応力を高めるアプローチが必要となります。

ものごとの受け止め方には、その人の性格や、生活環境、過去の経験、その時の体調や気分など複雑な要因が影響し、同じ出来事に対しても、「どうにかなるさ」と楽観的になれる人と、「どうしよう」と不安が強くなりがちな人など、受け止め方にパターンがあることが多くみられます。
自分の受け止め方や思考のパターンを見つけて、より適応的で柔軟な受け止め方をしていけると、気持ちや行動面でもよい変化が見られ、ストレスとも上手に距離をとれるようになるでしょう(認知行動療法的アプローチ)。
当院では認知行動療法は行っていませんが、そのエッセンスを用いながらみなさまのストレスへの適応力を高めていくお手伝いをしていきます。