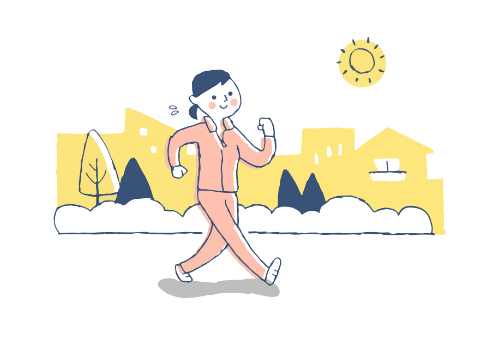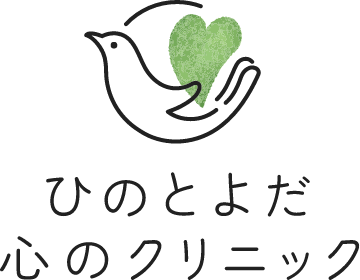不安症(不安障害)
不安症(不安障害)の症状・原因
大切な試験の前や、人前で発表しなければならない時、人は誰でも不安になります。不安そのものは私たちにとって必要なもので、不安があることで危険を回避したり、対策をとったり、失敗を防ぐことができるのです。しかし、不安が強すぎると日常生活が制限され、仕事や学業に影響が出てしまいます。そのような状態を不安症と言い、要因としては、心理的ストレス、性格傾向、環境的な要因、遺伝的な要因などが関係し、脳内の神経伝達物質の一つであるセロトニンのアンバランスが生じていると考えられています。
不安症には、社交不安症(社交不安障害)、パニック症(パニック障害)、広場恐怖症、限局性恐怖症、全般不安症(全般性不安障害)などがあり、よくみられる症状には以下のようなものがあります。

よくみられる症状
- いろいろなことがとにかく不安だ
- その不安や恐怖で落ち着かない、疲れやすい、いらいらする、熟睡できない
- 特定の状況に対する恐怖や不安があり、その状況を避けている
- 人の前に出たり、人に注目されると、極度に緊張したり、周りの目が気になってしまう
- 公共交通機関の利用が恐怖あるいは不安である
- 広い場所、囲まれた場所は恐怖あるいは不安である
- 急に不安が高まり、呼吸が早くなりドキドキする
不安症(不安障害)の診断
ここでは、代表的な2つの不安症について診断基準をご紹介します。
DSM-5による社交不安症の診断基準
他者の注目を浴びる可能性のある1つ以上の社交場面に対する、著しい恐怖または不安。
振る舞いあるいは不安症状を見せることが否定的な評価をうけることになると恐れている(恥をかいたり恥ずかしい思いをするだろう、拒絶されたり、他者の迷惑になるだろう等)。
その社交的状況はほとんどいつも恐怖または不安となる(注:子どもの場合、泣く、かんしゃく、凍りつく、まといつく、縮みあがる、または、社交的状況で話せないという形で、その恐怖または不安が表現されることがある)。
その社交的状況は回避され、あるいは恐怖または不安を感じながら耐えている
その恐怖や不安は、その社交的状況がもたらす現実の危険や、その社会文化的背景に釣り合わない
その恐怖、不安または回避は持続的であり、6か月以上続く。
その恐怖、不安または回避は、臨床的意味のある苦痛をもたらし、社会的、職業的あるいはほかの重要な場面で、その人の機能障害をおこしている。
その恐怖、不安、または回避は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。
その恐怖、不安、または回避は、パニック症、醜形恐怖症、自閉スペクトラム症といった他の精神疾患の症状では、うまく説明されない。
他の医学的疾患(例:パーキンソン病、肥満、熱湯や負傷による醜形)が存在している場合、その恐怖、不安、または回避は、明らかに医学的疾患とは無関係または過剰である。
DSM-5による全般不安症の診断基準
(仕事や学業などの)多数の出来事または活動についての過剰な不安と心配(予期憂慮)が、起こる日のほうが起こらない日より多い状態が、少なくとも6ヵ月間にわたる。
その人は、その不安を抑制することが難しいと感じている。
その不安および心配は、以下の6つの症状のうち3つ(またはそれ以上)を伴っている(過去6ヵ月間、少なくとも数個の症状が、起こる日のほうが起こらない日より多い)。 注:子どもの場合は1項目だけが必要
- ( 1 ) 落ち着きのなさ、緊張感、または神経の高ぶり
- ( 2 ) 疲労しやすいこと汗
- ( 3 ) 集中困難、または心が空白となること
- ( 4 ) 易怒性
- ( 5 ) 筋肉の緊張
- ( 6 ) 睡眠障害(入眠または睡眠維持の困難、または、落ち着かず熟眠感のない睡眠)
その不安、心配、または身体症状が、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
その障害は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的疾患(例:甲状腺機能亢進症)の生理学的作用によるものではない。
その障害は他の精神疾患ではうまく説明されない
*DSM-5:Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
不安症(不安障害)の治療
薬物療法
不安症の発症には、うつ病と同じく「セロトニン(脳内の神経伝達物質)」が、影響しているといわれています。そのため、不安症に対する薬物療法としては、抗うつ薬の一種である選択的セロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor:SSRI)
や、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor)が第一選択薬となります。SSRIやSNRIの内服にて不安症状が消失したあとも一定期間は内服を継続し、不安をコントロールできる良い状態を維持していきます。その後はご希望もお聞きしながら薬の量を徐々に減らし、可能な場合は内服薬の中止を目指します。その間症状がぶり返すようであれば、必要最小量の服薬を継続します。なお、SSRIはその効果が表れるまでにはおおよそ1~2週間かかることから、初期のつらい不安症状に対して一時的にベンゾジアゼピン系抗不安薬を併用することがあります。
非薬物療法
非薬物療法としては、不安をコントロールする「認知行動療法」が推奨されています。認知行動療法とは、認知(ある出来事に対しての受け取り方や見方のこと)に働きかけて、バランスのいい考え方ができるようにしていく療法のことです。より柔軟な思考ができるようになることで、ストレスや不安を和らげる効果に期待できます。専門的な認知行動療法を受けることができなくても、認知行動療法の考え方を取り入れていくだけでも良いでしょう。
そのほか、リラクゼーショントレーニングや呼吸法などによって、不安と上手に付き合うことを目指します。